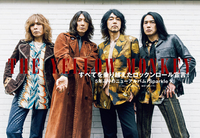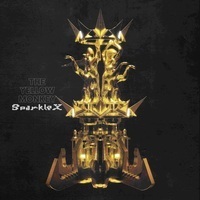19歳の時、THE YELLOW MONKEYを聴くようになった。
好きだったバンドマンたちが皆、口を揃えて「ルーツは、日本でいうとTHE YELLOW MONKEYとかですかね」なんていうから。
西暦で言うところの2010年。THE YELLOW MONKEYはとっくに解散していたが、彼らの音楽を聴いて育った世代が、頭角を現し始めていた頃だった。
だが、私にとってTHE YELLOW MONKEYはあくまで「好きなバンドマンが好きなバンド」でしかなかった。曲もライブもすごくかっこいいと思ったが、彼らは「映像の中の人」でしかなかった。
当時の私はとにかく、バンドを追いかけたかった。
好きなバンドが少しずつ知名度を上げて、会場の規模が大きくなって、チケットが争奪戦になっていくことが嬉しかった。ライブに通いたかった。チケットと500円玉を握りしめてライブハウスに並びたかった。新譜を楽しみにしたかった。
解散してるバンドを追いかけてる場合じゃなかった。
しばらくして、
大好きだったバンド達は面白いくらいに次々と解散していった。
バンドは解散するものだと知った。
あっけなく。
そして、私はだんだん音楽を「好き」「嫌い」ではなく、「良い」とか「売れそう」という視点でしか語らなくなった。
フェスやライブに行っても「このバンドは売れるな」「あと1年もしたら引っ張りだこだな」「この曲はフェスで映えそう」なんて偉そうに言っちゃうタイプの、わかってる風なんちゃって音楽評論家になっていた。
本当に好きだったのかはわからない。
でも、それなりに気に入ったり、飽きたりしながら、毎日服を着替えるように、靴を履き替えるようにいろんな音楽を聴いた。
2016年1月8日
THE YELLOW MONKEYの復活が発表された。
インターネット上のありとあらゆる場所で興奮気味に語られる「私とTHE YELLOW MONKEYの思い出」を横目で見ながら、なんちゃって音楽評論家は完全に蚊帳の外だった。
だって、私はTHE YELLOW MONKEYとの思い出なんて何一つ持ってなかったから。いつだって彼らは映像の中の人。自分の人生とはリンクしてなかった。
「青春が帰ってくる!」みたいな人たちの、その熱量をとても羨ましく、そして、そこまで熱くイエモンを語れない自分にどこか引け目を感じながら、静かに5月を待った。
2017年5月12日
SUPER JAPAN TOUR
代々木体育館2日目
THE YELLOW MONKEYは、ほとんど変わらない姿で幕の向こうから現れた。
映像で見たまま、ホンモノだった。
そして、めちゃめちゃにかっこよかった。
痺れるほど。
本当に居た。
「伝説」なんかじゃなかった。
自分の中には、彼らとの思い出なんて一切無かったはずなのに、それなのに涙がたくさん出てきた。
「ずっと待ってたよ」と泣いてる人たちの前で申し訳ないと思いながら、その涙を止めることができなかった。
帰り道、イヤホンを耳に入れて「SPARK」を再生したら、今までと全く違う音が聴こえてきた。音の一粒一粒が、遠くで近くで、立体的に鳴り出して、まるで違う曲に聴こえた。まさに血が巡るように音が全身を駆け抜けて、悲しいわけでもないのに、訳も分からないままにまた泣いたのを覚えている。
この日のことはおそらく一生忘れない。
私の人生に「純粋に音楽を好きでいること」が戻ってきた日だった。
こうして私は、なんちゃって音楽評論家じゃいられなくなった。
先日行われた東京ドーム公演では、
アンコールの1曲めにSO YOUNGが演奏された。
誰にでもある青春 いつか忘れて
記憶の中で死んでしまっても
あの日僕らが信じたもの
それはまぼろしじゃない
残念ながら、私の青春に彼らは居なかったが、
私が信じた「私の青春」、それは決して幻なんかじゃないよ。と彼らは教えてくれた。
この曲を出した後、一度は解散したが、再びファンの前に帰ってきた4人の姿が、それをしっかりと証明していた。
幻なんかじゃない。
置き去りにした過去を拾い上げて、自分たちの手で今とつなぎ合わせるその姿には、心打たれずにはいられなかった。
そして、彼らは来年から新しいアルバムの制作に入ることを発表した。
去年から鳴り止まない「復活おめでとう」「おかえり」という拍手を自分たちの手で制し、ついに贔屓目なしの真剣勝負を始めようということだ。
おそらく私は、彼らのその新譜を「いい」「悪い」「売れそう」みたいな基準で語ることはできない。
もうすっかりただのファンになったから。
それで、いい。
THE YELLOW MONKEYは、私の人生に根を張るくらいにリンクし始めたから。
なんちゃって音楽評論なんてしてる場合じゃない。
彼らを追いかけることで毎日忙しいのだ。
この作品は、「音楽文」の2018年1月・月間賞で入賞した東京都・汐風さん(28歳)による作品です。
音楽評論家じゃいられない - THE YELLOW MONKEYなんて、ただの「伝説」だと思ってた。
2018.01.10 18:00